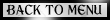
MURMUR
2000.08.05 (SUT.)
異次元の海月(くらげ)
その世界は4階にあり、窓からはとなりの壁面とわずかな空が見える。ベッドに横たわった視界に してみれば、空の割合はもう少し多いのかもしれない。
一日目の朝は「起こして」と怒っていた。信じてもまただまされる。警備の人に手伝ってもらえば大丈夫。 そうでないなら自分でタクシーを呼んで家に帰ると。点滴を無理矢理に引っこ抜いて這ってでも家に帰るから、 と叫んでいた。 夕刻にはまるで見世物のように指さされ、泣きながら手を振ったという。
二日目の朝は、いつかのように家族で旅行へ行こうとしていたが、娘たちはこれもまたよくあることだが 某かの理由で機嫌を損ねていてなかなか準備は捗らない。おいしいものも食べたいし、ゆっくり買い物も したいのに。ここで食事などしている時間はない。拍手。ほら拍手をしなさい。笑っている。 となりの病棟の天辺と空の間ぐらいを近所の誰其さんがおめかしして歩いている。本家の娘たちがきた。 その人に頼めと言う。
昼になるとロシアで海を見ていた。眠っている間はせめて欧州やあちこちへ旅行している夢を見てほしい、 と思った。願いが叶ったように思い、哀しくもうれしく感じる。となり町の某さんは足が悪いと聞いた。 そこに今立っているのは誰だろう。
三日目、いつもその人生は薬なのだ。気になるのは薬を飲まなければならない、ということばかり。 血糖値を下げる注射をしてくれた看護婦さんに「ありがとう」と言う。血圧を下げる薬にはもちろん 当然のように口を開く。明日の朝食べるものがない。今までこんなに頻繁に会いにきたことはないのに、 不安だ。頭ではわかっていることもどうしてもイライラするし気持ちが沈む。ずっと国立療養所で時間を過ごす あの子は腕が一本なかっただろうか。
それでも異次元の扉は少しずつ少しずつ、その世界に取り残されることなく、閉じつつあるのかもしれない。 奪われることの比率があまりにも大きく感じられる。だからこれからはささやかな砂のように小さな安らぎを ひとつずつ噛み締めて日々は続くに違いない。 心無い誰に対するよりも、謂れない何に対するよりも 潤いの雨は一粒でも多く降りそぼり、悪意に満ちた何かが存在するのであればそのすべてを我々海の兵隊か 身を賭して引き裂いて、切り裂いて、荒々しい波をも厭わない深い海を守ることとなるだろう。 そう感じたのだった。